Archive for the ‘刑事事件’ Category
【事例紹介】心霊スポットに訪れた人からお金を脅し取った事例
【事例紹介】心霊スポットに訪れた人からお金を脅し取った事例

心霊スポットに立ち入った人から、示談金の名目でお金を脅し取ったとして恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
「心霊スポット」とされるホテル跡地に立ち入った若者から示談金名目で現金を脅し取ったなどとして、京都府警木津署は19日、恐喝などの疑いで(中略)容疑者(32)と(中略)容疑者(40)と(中略)容疑者(30)を逮捕した。(中略)容疑者は容疑を認め、(中略)容疑者と(中略)容疑者は否認している。
(12月19日 産経新聞 「廃ホテル侵入者に「前科がつく」 120万円恐喝容疑でユーチューバーら3人逮捕」より引用)
逮捕容疑は共謀し今年8~9月、京都府笠置町にあるホテル跡地に立ち入った20代男性ら4人に対し「不法侵入です」「前科がつく」などと脅し、示談金として計120万円を脅し取ったなどとしている。
木津署によると(中略)容疑者は今夏から、ホテル跡地の所有者から現場の管理業務を任されていた。(後略)
恐喝罪
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、簡単に説明すると、強盗罪にいたらない程度の暴行や脅迫を用いてお金などを受け取ると成立する犯罪です。
大まかに説明すると、強盗罪は抵抗できないような暴行や脅迫を用いてお金などを奪うと成立します。
ですので、恐喝罪が規定する暴行や脅迫は、強盗罪が成立するような抵抗できない程度には至らない程度のものになります。
暴行は、殴る、蹴るはもちろんのこと、腕をつかむ行為や髪の毛を引っ張る行為なども暴行にあたります。
また、相手に恐怖を感じさせる害を与える告知が脅迫にあたります。
今回の事例では、容疑者らが心霊スポットに訪れた被害者らに対して、「不法侵入です」「前科がつく」などと脅して計120万円を脅し取ったとされています。
他人の敷地に無断で侵入して「不法侵入です」や「前科がつく」などと言われれば、前科がついて将来を棒に振ってしまうのではないかと恐怖を感じるのではないでしょうか。
また、「不法侵入です」や「前科がつく」と言われただけでは、その場から逃げ出すなどできそうですから、抵抗できない程度とはいえないでしょう。
ですので、被害者に対して「不法侵入です」や「前科がつく」と言う行為は、恐喝罪で規定する脅迫にあたりそうです。
報道によると、容疑者らは示談金の名目でお金を受け取っているようですので、実際に容疑者らが被害者に対して「前科がつく」などと脅してお金を受け取ったのであれば、恐喝罪が成立する可能性があります。
肝試しと建造物侵入罪
今回の事例では、事件現場が心霊スポットされているホテル跡地のようです。
報道によれば、容疑者らは被害者に「前科がつく」などと脅していたようです。
実際に被害者に前科がつくことはあるのでしょうか。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
大まかに説明すると、人が現在暮らしている家や宿泊しているホテルの一室などを住居、人が住んでいない空き家や使用していない別荘などを邸宅、住居や邸宅にあてはまらない建物を建造物といいます。
住んでいる人や管理している人の許可や正当な理由がなく、住居や邸宅、建造物に進入すると、住居侵入罪、邸宅侵入罪、建造物侵入罪がそれぞれ成立することになります。
今回の事例では、被害者はホテル跡地に立ち入っているようです。
このホテル跡地にはホテルだった建物が残っているようですから、建造物にあたると考えられます。
ですので、管理者に無断で侵入したり、侵入する正当な理由がない場合には、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
今回の事例では、容疑者の一人がホテル跡地の所有者から管理を任されているようですので、許可を得て立ち入ったわけではなさそうです。
また、立ち入った理由は報道からでは明らかではありませんが、仮に肝試し目的での侵入だった場合は侵入するための正当な理由とはいえないでしょうから、被害者は建造物侵入罪に問われる可能性があります。
もしも、今回の事例で建造物侵入罪が成立した場合には、有罪になれば前科がつくことになります。
このように、心霊スポットで廃墟などに進入する行為は建造物侵入罪など、何らかの犯罪が成立する可能性があります。
罪に問われたり、トラブル生まないようにするためにも、他人が所有する敷地内には無断で立ち入らないようにしましょう。
容疑をかけられたら弁護士に相談を
恐喝罪や建造物侵入罪は、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分を獲得することができれば、罰金刑や懲役刑は科されませんし、前科がつくこともありません。
示談を締結するためには示談交渉を行う必要がありますが、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえない場合があります。
ですが、加害者には連絡先を教えたくないが弁護士であれば教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
恐喝罪や建造物侵入罪などの刑事事件でお困りの方は、年末年始も即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
京都市東山区にある元交際相手の家に無断で侵入した男を逮捕
京都市東山区にある元交際相手の家に無断で侵入した男を逮捕

京都市東山区にある元交際相手の家に、無断で侵入した男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事案
京都府東山警察署は、京都市内に本社を置く製造メーカーに勤める会社員の男性(23)を住居侵入罪の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、京都市東山区で一人暮らしをしている元交際相手の女性宅に、交際当時に渡された鍵を使って無断で侵入した疑い。
帰宅した女性が、誰もいないはずの部屋の明かりがついており物音がすることに不振に思い110番したところ、駆けつけた警察官に男は逮捕された。
女性は、別れたあと男性に対し、自宅の鍵を返すよう再三要求していたとのこと。
(フィクションです)。
住居侵入罪とは
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法130条は、前段(「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」)で、住居侵入罪などを規定しています。
後段(「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」)で不退去罪を規定しています。
前段の侵入場所としては、①人の住居、②人の看守する邸宅、③建造物、④艦船が挙げられています。
①人の住居とは、人の起臥寝食(寝たり起きたり食事をすること)に使用されている場所をいいます。具体的には、自宅マンションや寮などです。
ちなみに、ホテルや旅館のように一時的に使用される場所であっても、人の住居にあたります。
②人の看守する邸宅は、守衛や管理人を置いている別荘などがこれにあたります。
③建造物とは、学校や工場など、住居や邸宅以外の建造物一般のことをいいます。
④艦船とは、軍艦及び船舶のことです。
本件では、男は一人暮らしをしている女性宅に侵入したとされています。
女性はそこで寝たり起きたり食事したりしているでしょうから、刑法130条の①人の住居にあたりそうです。
したがって、本件では住居侵入罪が成立する可能性があります。
侵入の意義
住居侵入罪の「侵入」とはどのような行為のこというのでしょうか?
現在の判例(最判58年4月8日など)は、住居権者の意思に反する立入りを「侵入」と理解しているようです(大塚ほか「基本刑法<第2版>」86頁)。
本件では、男は交際当時に渡された鍵を使って、無断で女性宅に立ち入ったようです。
男が住居権者である女性から鍵を渡されている点をふまえて、住居権者の意思に反する立入りではないと考えることはできるでしょうか?
たしかに、交際している期間については、鍵をわたされていたことから、男は自由に女性宅に立ち入ることを許されていたと解される余地がないとはいえないないでしょう。
しかし、女性が、男に対し鍵を返却するように再三求めていることからも明らかなように、交際期間終了後に関しては、女性は、男の女性宅への立入りを許していなかったといえるでしょう。
したがって、本件男性の女性宅への立入りは「侵入」にあたり、住居侵入罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
住居侵入罪のように被害者のいる犯罪では、被害者との間に示談を成立させることができるかどうかが重要となります。
示談が早期に成立すれば不起訴処分となる可能性があります。
ただし、加害者がきちんと反省し謝罪したいと思っていたとしても、相手方がこれに応じてくれる可能性は高くありません。
被害者からすれば、ついこの間自分の家にあがってきた人、が自分に接触しようとしているというだけで恐怖を感じて示談交渉をはじめることすら拒絶されかねません。
そこで、弁護士に示談交渉を一任されることをおすすめします。
加害者と直接連絡をとることに抵抗を感じる被害者も、弁護士とのやりとりであれば応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、起訴を防ぐことができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。
偽装心中!愛人をだまして一人で心中させた男が殺人罪で逮捕
偽装心中!愛人をだまして一人で心中させた男が殺人罪で逮捕

愛人をだまして一人で心中させた男が殺人罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事案
京都府伏見警察署は、京都市伏見区に住む薬品関係の会社を経営する男(45)を殺人罪の疑いで逮捕した。
京都府伏見警察署によると、男は妻子ある身であったが不倫関係にある秘書から「奥さんと別れて私と結婚してほしい。できないなら一緒に死のう」と心中を迫られた。
男は心中するつもりはなかったが、その場にあわせ「一緒に心中しよう」と答え、致死量を超える薬を2人分用意し、相手に先に飲ませて自殺させ、自分は飲まなかったとのこと。
(フィクションです)
殺人罪と自殺関与罪
刑法199条 殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
本件で男は、199条の殺人罪の嫌疑で逮捕されています。
しかし、亡くなった女性は、男が用意した致死量の薬を自ら飲んで自殺したとのことですので、殺人罪ではなく202条の自殺関与罪とはならないのでしょうか?
刑法202条 自殺関与罪
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ(…)た者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
202条の自殺関与罪は、さらに自殺教唆罪と自殺幇助罪に分かれます。
自殺教唆罪とは、自殺意思のない者を唆して自殺を決意させ、自殺を行わせることです。
自殺幇助罪とは、自殺の決意を有する者の自殺行為を援助し、自殺を遂行させることです。
本件では、女は自分から一緒に死のうと心中をもちかけていますから、男が一緒に死んでくれるという条件付きであるものの自殺の決意を有していたといえそうです。
加えて、男は、致死量の薬を用意して自殺行為を援助し、女に自殺を遂行させています。
したがって、202条の自殺幇助罪が成立するのではないでしょうか?
偽装心中
結論として、判例は、偽装心中のケースでは一貫して199条の殺人罪を適用しています。
最高裁は、女性から心中を申し出られ同意したが、途中で気が変わったのに後を追うように誤信させて女性のみに毒物を飲ませて死亡させた偽装心中の事案にて、被害者は加害者の欺罔の結果、加害者の追死を予期して死を決意したのであり、「その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思」であるから、殺人罪に該当すると判示しています(最判昭和33年11月21日)。
本件も、被害者の女性は、加害者の男性が一緒に死んでくれると騙されて、死ぬことを決意したようですから、仮に男に死ぬつもりがないと知っていれば、被害女性は死のうとはしなかったでしょう。
そうすると、被害女性の死ぬ決意は、真意に添わない重大な瑕疵ある意思といえます。
判例に従えば、本件でも殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。
身体拘束の長期化のおそれ
殺人罪は、刑法の規定する犯罪の中でも法定刑が重くなっていますから、裁判の結果下される量刑も重くなる可能性が高いため、逃亡のおそれがあるとして釈放や保釈が認められづらい犯罪です。
警察に逮捕された被疑者は、逮捕から72時間以内に、「勾留」という逮捕に引き続く10日間の身柄拘束の必要性について、検察官と裁判官から判断されます。
弁護士は、検察官と裁判官に対し、勾留に対する意見書を提出することができますから、このタイミングで釈放を求めることができます。
したがって、早い段階で弁護士に相談して、意見書を提出する機会を逃さないことが大切です。
仮に、釈放されずに起訴された場合、次にすることができることは裁判所に対する保釈請求です。
保釈が認められた場合、保釈金を支払うことで身体拘束から解放されます。
たしかに、殺人罪は釈放や保釈が認められずらいものの、絶対に釈放や保釈が認められないわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験のある法律事務所です。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。
【事例紹介】かばんに包丁を所持し、ユーチューバー逮捕
【事例紹介】かばんに包丁を所持し、ユーチューバー逮捕

ユーチューバーがかばんに包丁を所持したとして、銃刀法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
かばんに包丁を所持していたとして、京都府警右京署は17日、ユーチューバーの男(33)(右京区)を銃刀法違反容疑で逮捕した、と発表した。
(12月18日 読売新聞オンライン 「「死ぬために持っていた」包丁を所持していたユーチューバーの男を逮捕、母が京都府警に通報」より引用)
発表によると、男は(中略)京都市右京区の駐輪場前で、包丁(刃渡り約15センチ)1本を所持した疑い。男の母親が「息子が包丁を持って出かけたかもしれない」と通報し、駆けつけた署員が職務質問の上、現行犯逮捕した。
(中略)「死ぬために持っていた」と容疑を認めているという。
刃物の所持と銃刀法
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」といいます。)第22条では、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定しています。
簡単に説明すると、仕事で使用する場合や正当な理由なく、刃の長さが6センチを超える刃物を持ち歩くと銃刀法違反が成立します。
今回の事例では、容疑者がかばんに包丁を所持していたとして、銃刀法違反の容疑で逮捕されたようです。
今回の事例で銃刀法違反は成立するのでしょうか。
容疑者が所持していた包丁は刃渡り約15センチとのことですので、銃刀法で携帯の認められていない刃物に該当する可能性が高いでしょう。
次に正当な理由などがあるかどうかについて考えていきましょう。
報道によれば、容疑者が包丁を所持していた理由は「死ぬために持っていた」ようです。
銃刀法で認められるような正当な理由とは、例えば、草刈りのために鎌を携帯する行為が当てはまると考えられます。
今回の事例のような、死ぬために刃物を所持することは正当な理由には当てはまらないでしょうし、仕事のために持っていたわけでもないようですから、実際に容疑者が死ぬために包丁を所持していたのであれば、銃刀法違反が成立する可能性があります。
銃刀法違反と不起訴処分
銃刀法違反が問題になるケースとして、車から刃物を降ろし忘れたことで銃刀法違反の罪に問われてしまうケースが存在します。
例えば、草刈りを行うために鎌を車に乗せ、草刈りが終わった後も鎌を降ろし忘れて車を使用していた場合などがこのケースにあたります。
草を刈りに行く道中や帰る際には「草刈りを行うため」という鎌を携帯する正当な理由があるといえますが、草刈りが終わった翌日以降も車に鎌を乗せた状態が続いてしまうと、「草刈りを行う」という正当な理由がなくなるわけですから、正当な理由なく刃物を携帯することになり、銃刀法違反が成立してしまうおそれがあります。
今回の事例や上記のケースのような場合では、銃刀法違反で有罪になることは避けられないのでしょうか。
結論から言うと、銃刀法違反で有罪になることを避けられる可能性があります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
例えば、今回のような事例では、今後は通報をした母親が容疑者が刃物を持って出歩かないように監視監督を行うなど、再犯防止に尽くすことを弁護士が検察官に訴えることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
また、不起訴処分を得るためには、弁護士の処分交渉だけでなく、取調べ対応も重要となります。
取調べでは、供述調書と呼ばれる裁判で使用される証拠を作成します。
この供述調書は一度不利な内容で作成されてしまうと、その内容を覆すことは容易ではありません。
供述調書は裁判だけでなく、検察官が起訴の判断を行う際の判断材料になる可能性もありますから、不起訴処分を目指す際には取調べ対応もかなり重要になってきます。
取調べの際には、警察官や検察官が、思い通りの筋書きにしようと供述を誘導してくることが多々あります。
誘導に乗ってしまうことで、不利な供述調書の作成につながる可能性が高くなりますから、そういったリスクを避けるためにも、あらかじめ弁護士と供述すべき内容と黙秘すべき内容の精査を行っておくことが重要です。
取調べ前に弁護士と打ち合わせを行うことで、不利な供述調書の作成を防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
数多くの事件で不起訴処分を獲得してきた経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
銃刀法違反事件やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
人気ラーメン店で食中毒⁉業務上過失致傷罪で書類送検
人気ラーメン店で食中毒⁉業務上過失致傷罪で書類送検

人気ラーメン店で食中毒が発生し、店長が業務上過失致傷罪で起訴された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事案
ラーメンの激戦区として知られる京都市左京区にある人気ラーメン店「さしすせそ」本店で、食中毒が発生した。
「さしすせそ」本店でラーメンを食べた人たちが、腹痛や下痢を訴え病院に運ばれたことがきっかけで保健所の検査が入り、同店の名物である生チャーシューを原因とする食中毒だとわかった。
厚労省は、豚肉の中心部の温度が63℃で30分以上加熱するよう求めているところ、同店の店長は、この基準を知らなかったためにを同基準を満たさない調理をしていたとのこと。
京都府下鴨警察署は、同店長を業務過失致傷罪で書類送検した。
(フィクションです。)
業務業過失致傷罪とは
刑法211条前段
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
業務上過失致傷罪の「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれのあるもの」です(最判昭和33年4月18日)。
上記の業務概念は①社会生活上の地位に基づくこと、②反復継続性があること、③生命・身体に対し危険な行為であること、の3つの要素からなりたっています。
本件で書類送検されたのは、ラーメン店の店長ですから、飲食業者という社会的地位に基づいてラーメンを製造し提供していると言えます(①)。
また、ラーメン店を開業しているわけですから、反復継続性も問題なく認められるでしょう(②)。
それでは、ラーメンの製造、提供は③生命・身体に対し危険な行為といえるのでしょうか?
ラーメンの製造、提供は、厚労省の基準にしたがって適切に調理されている限り、危険な行為にはならないといえるでしょうが、今回のように食べ物は適切に調理されなかった場合、食中毒を招き腹痛や下痢、最悪の場合には死に至ることさえあります。
したがって、ラーメンの製造、提供は、生命・身体に対し危険な行為であるといえるでしょう(③)。
ですので、本件のラーメン店「さしすせそ」の店長がラーメンを製造する行為は業務上過失致傷罪の「業務」に該当する可能性が高いといえます。
加えて、業務上過失致傷罪は、「業務上必要な注意を怠」ったといえることが必要です。
本件に即していえば、ラーメン店「さしすせそ」の店長は、チャーシューを作るにあたって、豚肉の中心部の温度が63℃で30分以上加熱する必要があったところ、それを知らずに不適切な調理をしていたようですので、業務上必要な注意を怠っていたといえそうです。
今回、業務上過失致傷罪が問題となっていますから、その成立には傷害結果が生じたことも必要です。
傷害とは人の生理機能を侵害することをいいます(大判明治45年6月20日)。
本件の被害者は腹痛や下痢をうったえていますから、店長は、人の生理機能を侵害したと評価される可能性があります。
以上から本件では業務上致傷罪が成立する可能性があります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談を
業務上過失致傷罪は被害者のいる犯罪です。
早い段階で被害者に真摯な反省と謝罪を伝え、示談を成立させることで事件化を防いだり不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
仮に、起訴されたとしても示談が成立していることをふまえて量刑が軽くなる能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上過失致傷罪を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、事件化や起訴を防ぐことができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。
電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例
電動キックボードでひき逃げ事故を起こした事例

事例
仕事終わりのAさんは帰宅するべく、京都市右京区の路上を電動キックボードで走行していました。
雨で視界が悪かったことで前方を歩いている歩行者の姿に気づかずに歩行者とぶつかり、ぶつかった衝撃で歩行者は転倒してしまいました。
怖くなったAさんは歩行者の救護や警察への事故の報告をすることなく帰宅しました。
後日、京都府右京警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんがぶつかった歩行者が全治10日間のけがを負ったこと、事故当時の話しを聞くために京都府右京警察署まできてほしいことを伝えられました。
Aさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
電動キックボードと人身事故
一部運転をするのに免許を必要としないものもある電動キックボードですが、道路交通法では原動機付自転車に分類されます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定しています。
簡単に説明すると、周囲の安全確認など運転をするのに必要な注意を払わずに人にけがをさせた場合には過失運転致傷罪が成立します。
原動機付自転車は自動車運転処罰法が規定する「自動車」にあたります(自動車運転処罰法第1条1項)ので、電動キックボードで運転上必要な注意を払わずに事故を起こして人にけがをさせると、過失運転致傷罪が成立することになります。
今回の事例では、Aさんが前方の歩行者に気づかずにぶつかり、全治10日間のけがを負わせています。
雨が降っていて視界が悪かったとはいえ、きちんと前方を確認していれば歩行者の存在に気づけたでしょう。
運転をするうえで前方に人がいないかを確認することは確実に必要な行為だといえます。
ですので、Aさんは電動キックボードを運転するうえで必要な注意を怠り、人にけがを負わせたといえますので、過失運転致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
電動キックボードとひき逃げ
交通事故を起こした場合には、負傷者の救護と警察への事故の報告を行わなければなりません。(道路交通法第72条1項)
負傷者の救護や警察への事故の報告をしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護と警察への事故の報告は義務ですので、ひき逃げをした場合には、道路交通法違反の罪が成立することになります。
今回の事例では、Aさんが電動キックボードで歩行者にぶつかり、歩行者にけが等の確認や警察への事故の報告をすることなく、事故現場を去っています。
電動キックボードといえど、事故を起こして負傷者の救護や警察に事故の報告を行わなければひき逃げになりますから、事例のAさんは過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反の罪に問われることになるでしょう。
自らの運転が原因で人にけがを負わせ、救護をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
警察署に事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)
電動キックボードで事故を起こした場合には
最近では京都市内でも電動キックボードを運転する方を目にすることが多くなりました。
運転をするのに免許が不要な電動キックボードもある影響か、交通ルールを守っていない方を時々見かけます。
免許が不要な電動キックボードであっても、人身事故を起こした場合には過失運転致傷罪などの罪に問われる可能性がありますし、ひき逃げをした場合には過失運転致傷罪だけでなく道路交通法違反に問われる可能性もあります。
当然、過失運転致傷罪やひき逃げによる道路交通法違反で有罪になれば、刑罰が科されますし、前科も付くことになります。
前科が付くことで、就職活動に悪影響を及ぼしたり、会社を解雇されるおそれもあります。
電動キックボードの運転で将来を棒に振ることになる可能性もありますから、しっかりと交通ルールを守り、事故を起こさないような運転を心がけることが重要になります。
とはいえ、気を付けていても事故は起きるときがあります。
そういった場合には前科が付くことは避けられないのでしょうか。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられる場合があります。
刑事事件や交通事件では示談を締結することで、不起訴処分を得られる場合があります。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではないのですが、加害者が被害者と直接示談交渉を行うことで、被害者の感情を逆なでしてしまうこともありますし、予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
有利になる事情を弁護士が検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
示談でお困りの方、電動キックボードなどによる交通事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
『爆弾をしかけた』と私立大学に電話して業務を妨害した男
『爆弾をしかけた』と私立大学に電話して業務を妨害した男

『爆弾をしかけた』と私立大学に電話して業務を妨害した疑いで、男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事件概要
京都市左京区にある私立大学に、『大学構内に爆弾を仕掛けた。農薬の研究を中止しないと爆破する』などと電話があった。
京都府下鴨警察署は、威力業務妨害罪の疑いで、会社員の男性(34)を逮捕した。
(フィクションです)
威力業務妨害罪とは
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をすると成立する犯罪です(刑法234条)。
威力業務妨害罪が成立するための要件は以下の3つです。
①業務妨害手段として「威力」を用いたこと
②妨害の対象が「業務」であること
③妨害行為により業務が妨害されるおそれがあること
①「威力」について
まず、威力とは人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを意味します。
具体的には、殴るなどの暴行を受けた場合や「殺すぞ」などと脅迫された場合のほか、多数人で集合して怒号する行為も含まれます。
近年の裁判例を見てみると、上記定義にぴったりあてはまらないような行為であっても、公然と行われる妨害行為を広く「威力」を用いたものとする傾向が見られます(中森「刑法各論」74頁、山口「基本判例に学ぶ」55頁)
本件の場合、男は仕掛けた爆弾を爆破すると脅迫しているので、業務妨害手段として「威力」を用いたと評価できるでしょう。
②「業務」について
次に、業務とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務とされています(大判大正10年10月24日)。
例えば、タクシーの運転手がお客さんを目的地まで運ぶための車の運転や、洋食屋さんの店員がお客さんに提供するオムライスをつくる行為などは業務にあたります。
逆に、休日にツーリング目的で自家用車を運転する場合や、お母さんが夕食にオムライスをつくる行為は、社会生活上の活動ではないため業務に該当しません。
本件では、男が脅迫の電話をした先である大学では、大学職員や研究者が働いています。
彼らは継続して大学の事務手続きや研究などをしているわけですから、社会生活上の活動を継続して行っているといえますので、彼らの仕事は業務妨害罪における業務に該当します。
③妨害行為により業務が妨害されるおそれがあること
本件のように、大学に爆破予告がされた場合、大学職員は脅迫電話への対処のため学生等を非難させたり警察に通報したり、本来すべき業務に支障をきたす危険性があります。
研究者も本来すべき研究活動を中止して、避難せざるをえないかもしれません。
したがって、本件の男の爆破予告は業務を妨害するおそれがあったといえるでしょう。
以上より、本件では業務妨害罪が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法233条234条)
ですので、威力業務妨害罪で有罪になった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
弁護士に相談して事件の早期解決を
威力業務妨害罪は被害者が存在する犯罪です。
被害があればその被害弁償をして被害者と示談を成立させることが、事件の早期解決にとって重要となります。
被害届が出される前に示談が成立すれば、警察沙汰にならずにすむかもしれませんし、仮に事件化した後に示談が成立した場合でも起訴前であれば、不起訴処分となるかもしれません。
もっとも、爆破予告された被害者からすると、加害者と直接連絡をとることを怖いと思うのが自然ですし処罰感情も高いでしょうから、示談交渉に応じてくれない可能性があります。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、威力業務妨害事件を含む豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、事件化や起訴を防ぐことができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、0120-631-881にて受け付けております。
【事例紹介】息子の知人を装い、高齢女性から現金をだまし取ったとされる事件
【事例紹介】息子の知人を装い、高齢女性から現金をだまし取ったとされる事件
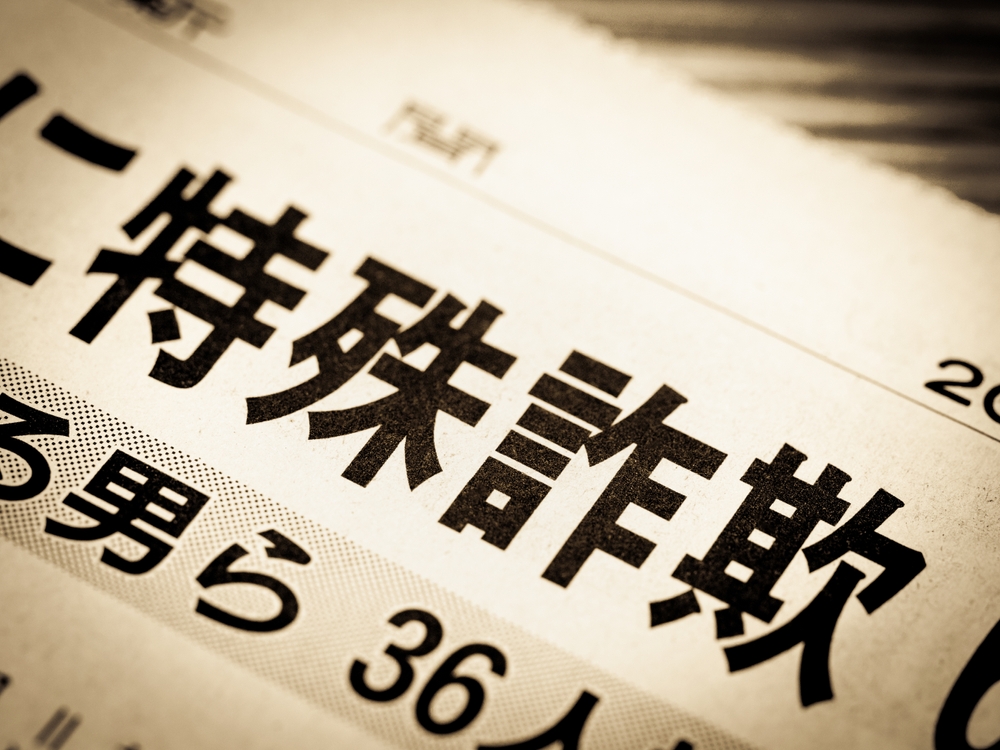
息子の知人を装い、高齢女性から現金をだまし取ったとされる事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
高齢者から多額の現金をだまし取ったとして、京都府警組対2課と東山署は11月28日、詐欺の疑いで、(中略)再逮捕した。府警は約20人でつくる特殊詐欺グループの首謀者とみている。
(11月28日 京都新聞「 『息子ががん』と高齢女性にうその電話、現金だまし取る 詐欺容疑で暴力団員を再逮捕」より引用)
再逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀し、昨年12月16日、三重県鈴鹿市の女性(79)宅に息子や医師を名乗り「カードをなくし、至急現金が必要」「息子さんが喉のがんになった」などとうその電話をかけて200万円を詐取。同様の手口で同17日、京都市上京区の女性(81)から140万円をだまし取った疑い。「一切関わっていない」と容疑を否認しているという。(後略)
詐欺罪とは
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。
欺罔行為とは?
人をだます行為がすべて、詐欺罪となりうる欺罔行為となるわけではありません。
詐欺罪となりうる欺罔行為とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
例えば、機械は錯誤に陥りませんから、他人のキャッシュカードを使ってATMからお金を引き出す行為は欺罔行為とならず、詐欺罪が成立することはありません。
本件報道によると、容疑者は氏名不詳者等と共謀し、被害者にうその電話をかけて金銭をだまし取ったとされています。
仮に被害者をだまして錯誤に陥らせることで金銭を交付させようとして、うその電話を掛けたのであれば、詐欺罪が規定する欺罔行為があったとし判断される可能性があります。
処分行為とは?
上述の通り、詐欺罪が成立するためには、欺罔行為により錯誤に陥った被害者が、錯誤に基づいて処分行為を行い、その処分行為により財物が加害者に移転する必要があります。
詐欺罪における処分行為とは、錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物を終局的に相手方に移転する行為のことをいいます。
例えば、試着した服を着て逃走する意図を有していた者に対して、店員がした試着の許可は、処分行為とはいえません。
店内で試着を許可するだけでは、店員の意思によって服を終局的に相手方に移転したとはいえないからです。
本件では詳細は不明ですが、金銭を被害者からだまし取ったとされています。
仮に、被害者宅にまでやってきた容疑者等に対し現金を手渡ししたのであれば、処分行為があったとして詐欺罪が成立する可能性があります。
一度金銭を加害者に渡した場合、簡単にその場から離れて持ち逃げすることができ、被害者が保持したり取り返すことは困難なため、金銭を終局的に加害者に移転したと評価される可能性があるためです。
なるべく早く弁護士に相談を
詐欺罪のように被害者のいる犯罪では、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
というとのは、早期に示談が成立していれば不起訴となる可能性がありますし、起訴後に示談が成立した場合でも、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があるからです。
もっとも加害者が独力で示談交渉をすすめることは通常困難です。
詐欺罪の嫌疑がかけられた場合、本件のように逮捕されることが多く、逮捕された状態で示談交渉を進めることは非常に困難です。
逮捕されずに在宅で捜査が行われる場合でも、被害者は自分をだました相手に強い処罰感情を有している可能性が高いですから、直接接触しようとしても交渉のテーブルに着くこと自体拒絶されかねません。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
直接加害者とやり取りすることに抵抗を感じる被害者でも、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、詐欺事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分や罪の減軽、執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
【事例紹介】生後10か月の息子を暴行してケガを負わせた事件
【事例紹介】生後10か月の息子を暴行してケガを負わせた事件

生後10か月の次男を暴行して意識不明となるケガを負わせた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(前略)生後10カ月の次男に暴行し意識不明となるけがを負わせたとして傷害の疑いで、(中略)容疑者(28)を逮捕した。
(12月1日 京都新聞「息子に障害疑い、28歳父親逮捕」より引用)
容疑を認めており、県警は動機や、日常的に虐待がなかったかどうかを調べる。
逮捕容疑は11月30日午前、自宅で次男(中略)の頭をソファの肘かけに打ち付け、急性硬膜下血腫のけがを負わせた疑い。
(後略)
傷害罪とは
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の行為は、人の身体を「傷害」することです。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)
殴るなどして出血させたような外傷のある場合だけでなく、失神させたり、感染症にかからせる行為も傷害にあたります。
本件では、容疑者は、次男の頭をソファの肘かけに打ち付けて急性硬膜下血腫のケガを負わせたとされています。
急性硬膜下血腫とは、頭蓋骨の下にある硬膜と脳の間に出血が起こり、そこに出血した血液が急速にたまることいいます。
脳に損傷を与える可能性が高く、意識障害や記憶障害、身体の麻痺などの後遺障害を引き起こすおそれがあります。
本件報道のとおりであれば、次男は急性硬膜下血種を起こし意識不明の状態になったようですから、容疑者の行為は次男の生理的機能に障害を加えたものとして、傷害罪が成立する可能性があります。
逮捕されたらいつ家に帰れるの?
逮捕された場合、72時間以内に勾留されるかどうかの判断が下されます。
勾留とは、逮捕に続く身体拘束であり、10日間に及ぶ上、場合によってさらに延長されることさえあります。
このように身体拘束期間が長引いた場合、学生の場合は学校に行けなくなり、社会人の場合には仕事に行くことができなくなってしまいます。
結果、犯罪の嫌疑がかけられていることが知られてしまい、退学や解雇される可能性があります。
なるべく早く弁護士に相談を
早い段階で弁護士に依頼した場合、早期釈放のための活動を適時に行うことができます。
釈放の判断材料として、弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、釈放が認められることがあります。
この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますから、時間との勝負となります。
可能な限り早い段階で一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお電話ください。
お電話は、0120‐631‐881におかけください。
タバコを注意され逆上した男性が相手の自転車を破壊した事件
タバコを注意され逆上した男性が相手の自転車を破壊した事件

タバコを注意され逆上した男性が、相手の自転車を蹴って壊した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事案
京都市左京区にあるマンションの駐輪場でタバコを吸っていた住人(56)が、同マンションに住む大学生に喫煙を注意されて大声で激怒し、同大学生の自転車を蹴って前輪のホイールを変形させた。
加害者の住人は、騒ぎに気づいた周辺の住民からの通報でやってきた京都府下鴨警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕された。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪とは
器物損壊罪を規定する刑法261条は、「他人の物を損壊し、または傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」としています。
まず、ここでいう「他人の物」に公用文書、私用文書、建造物又は艦船は含まれません。
これらのものを壊すなどして使えなくした場合には、器物損壊罪ではない別の犯罪が成立します(刑法258条〜260条)。
次に、「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為のことを言います。
物理的にものを壊して使えなくさせる行為はもちろん、食器に尿をかける行為のように心理的に物を使えなくさせる行為も含まれます(大判明治42年4月16日)。
本件では、加害者は被害者の自転車を蹴って前輪を変形させたとされています。
前提として、自転車は公用文書等ではありませんから器物損壊罪の対象だと言えます。
自転車の前輪が変形した場合、前輪を左右から挟み込んでいるフロントフォークに引っかかり前に進めなくなったり、進めたとしても真っ直ぐ進めなくなります。
したがって、加害者が自転車を蹴った行為は、自転車を本来の用途通りに使えなくさせる行為、すなわち自転車を損壊する行為であり、器物損壊罪が成立する可能性があります。
親告罪とは
器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴されない犯罪です(刑法264条)。
告訴とは、被害者をはじめとする告訴権者が捜査機関に対して、犯罪にあったことを申し出て犯罪者の処罰を求めるための手続きです。
被害届という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
被害届は、犯罪にあったことを捜査機関に申し出る点で告訴と共通しますが、犯人の処罰を求めているということまで意味するものではない点などで異なります。
本件では、被害にあった大学生が告訴をしない限り検察官は起訴することができないこととなります。
なるべく早く弁護士に相談を
起訴されなかった場合、有罪となることも前科がつくこともありません。
したがって、器物損壊罪を犯してしまった場合、告訴されるかどうかが非常に大きな意味を持ちます。
仮に、一度告訴されたとしても、起訴される前に被害者が告訴を取り下げてくれれば、やはり検察官は起訴することができなくなります。
したがって、器物損壊罪を犯してしまった場合、被害者に謝罪や被害弁償をして告訴をしないように、仮にすでにされていた場合は取り下げてもらうようにお願いする必要があります。
もっとも、加害者本人が直接被害者側とこのような示談交渉をするのは望ましくありません。
被害者は通常、加害者に対して強い処罰感情を有していることが想像されますから、示談交渉に応じてもらえない可能性が高いです。
仮に、応じてもらえたとしても、相場より高い被害弁償の額を要求され、折り合いがつかず交渉が決裂し告訴される可能性もあります。
そこで、示談交渉のプロである弁護士にお任せすることをおすすめします。
第三者的立場から弁護士が被害者と交渉をすることで、被害者が感情的になり生産的でない言動をすることを避けることができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕前であれば、初回無料で弁護士に相談していただけます。
逮捕後の場合には、弁護士を留置場まで派遣させていただきます。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
詳しくは0120-631-881までお電話ください。





