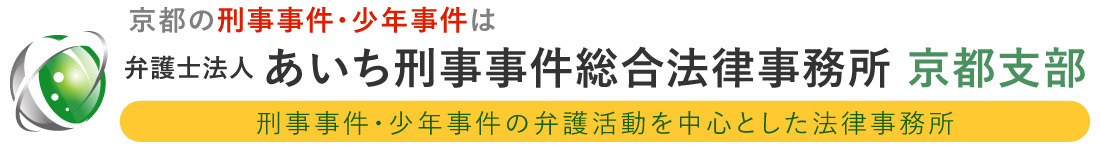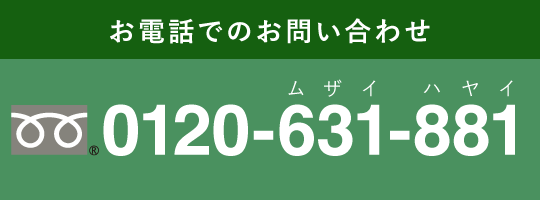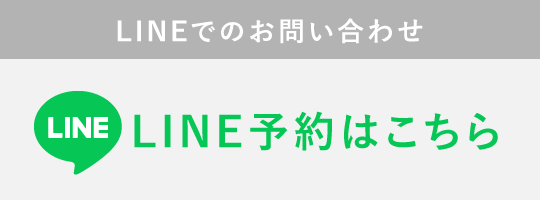お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)②
お年玉の兄弟喧嘩から少年事件(傷害事件)に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
会社員のBさんは、妻のCさんと息子のAさん(17歳)・Vさん(15歳)の4人で京都市西京区に住んでいます。
年が明け、AさんとVさんはBさん・Cさんや親戚からお年玉をもらいました。
しかし、もらったお年玉の額の違いでAさんとVさんは口論になり、取っ組み合いの兄弟喧嘩となってしまいました。
そして結果的にAさんがVさんを一方的に殴る展開になってしまいました。
Bさん・Cさんは兄弟喧嘩を止めようとしましたが、Aさんが激しく怒っていた様子だったため、これ以上ひどいことにならないようにしなければいけないと考え、京都府西京警察署に通報しました。
Aさんは駆け付けた警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさん・Cさん・Vさんはまさか兄弟喧嘩でAさんが逮捕されることになるとは思わず、慌ててしまいました。
Bさんらは、Aさんの学校が始まる前になんとか釈放してもらえないか、兄弟喧嘩であることからどうにか穏便に済ますことはできないか、と少年事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件と捜査段階の身体拘束
逮捕が行われるには、その犯罪の嫌疑がかかる相当性と逮捕の必要性(逃走や証拠隠滅のおそれがあること)があることが必要です。
例えば、今回のAさんのケースでは、傷害事件の加害者(今回ではAさん)と被害者(今回ではVさん)が同居しているという状態です。
刑事事件・少年事件では、加害者と被害者は接触しないようにするのが通常です。
というのも、加害者と被害者が容易に接触できてしまえば、加害者から被害者へ証言の変更を迫る等できてしまうおそれがあると考えられるからです。
刑事事件・少年事件での「証拠」とは、物としてある証拠品だけではなく、関係者の証言も「証拠」の扱いとなります。
そういったことから、Aさんのような状況では証拠隠滅のおそれがあると判断されたと考えられます。
この逮捕が警察によって行われた場合、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を検察へ送るか釈放するかを決めます。
検察へ送る(これを「送検」と言います。)場合、検察官は送致を受けた時からさらに24時間以内に勾留という逮捕に引き続くより長い身体拘束をする必要があるかどうか判断します。
検察官が勾留の必要があると判断すれば、検察官は裁判所へ勾留請求を行います。
逆に、勾留の必要はないと検察官が判断すれば、被疑者はそこで釈放されることとなります。
弁護士が釈放を求める活動の中で最も早く働きかけられるのはおそらくこの段階でしょう。
検察官が勾留請求をするかしないかの判断前であれば、検察官に向けて勾留請求をせずに釈放してほしいと主張する活動をすることができます。
特に少年事件においては、成人の刑事事件と違い、勾留請求は「やむを得ない場合」でなければできないことになっています。
少年法43条3項
検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。
ですから、この「やむを得ない場合」に本当に当たるのかどうかを確認してもらい、勾留請求をしないよう求めていくことが考えられます。
検察官が勾留請求をした場合、その勾留請求を認めて勾留するかどうか判断するのは裁判所の裁判官です。
ここでも、弁護士は検察官の勾留請求を認めないよう裁判官に主張していくことができます。
少年事件においては、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことだけでなく、前述の「やむを得ない」場合に当たらない事情についても主張していくことになるでしょう。
勾留がついたということになれば、まずは最大10日間の身体拘束を受けることになり、さらに最大で10日間勾留を延長することができます。
つまり、被疑者として警察や検察で捜査される場合、逮捕と勾留合わせて最大23日間の身体拘束を受ける可能性があるということになります。
また、少年事件の場合、この勾留について、「勾留に代わる観護措置」という措置が取られることもあります。
これは少年法に定められている措置で、成人の刑事事件にはない措置です。
少年法43条1項前段
検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第17条第1項の措置を請求することができる。
※注:「第17条第1項の措置」とは、観護措置のことを指します。
少年法44条
3項 前項の措置の効力は、その請求をした日から10日とする。
※注:「前項の措置」は勾留に代わる観護措置のことを指します。
簡単に言えば、被疑者段階で取られる勾留の手続きの代わりに、少年法の「観護措置」(詳しくは次回の記事で説明します。)を取る措置ということです。
勾留に代わる観護措置となった場合、被疑者である少年は、警察署の留置所ではなく少年鑑別所に留置されることになり、先述した勾留の延長はできず、最大10日間の身体拘束をされることになります。
そして、その10日間が経過し家庭裁判所に送致された後は、自動的に今度は少年法のいう「観護措置」に切り替わることになります。
少年事件では、被疑者段階でも勾留に「やむを得ない場合」という条件が加えられていたり、勾留に代わる観護措置という独特な措置があったりと、成人の刑事事件とはところどころ異なる部分があります。
だからこそ、少年事件は少年事件に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も専門に扱う弁護士が迅速な対応を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。