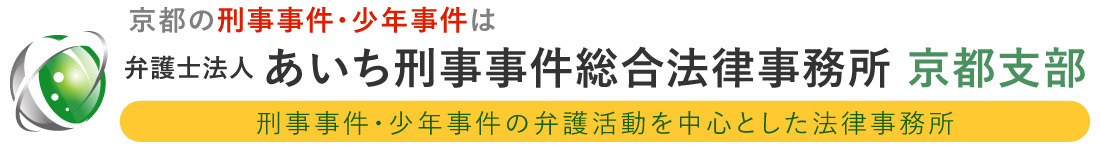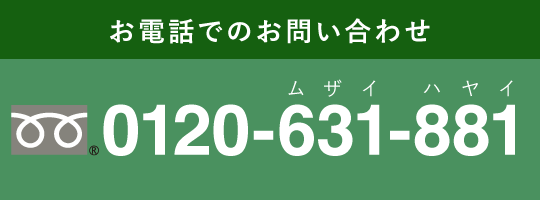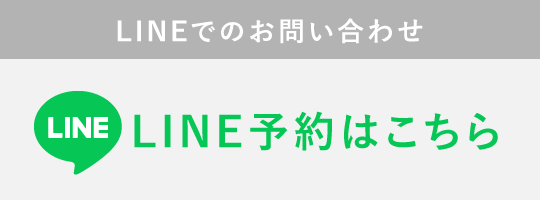3歳男児を浴槽に放置し溺死させた容疑で保護責任者遺棄致死罪で逮捕された事件

3歳男児を浴槽に放置し溺死させた容疑で保護責任者遺棄致死罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事案
交際相手の息子を浴槽に放置して溺死させたとして、京都府警宇治署は30日、保護責任者遺棄致死の疑いで、宇治市の建設業の男(29)を逮捕した。
(京都新聞7月31日「3歳男児を浴槽に放置し溺死させた疑い」より引用)
逮捕容疑は30日未明、男の自宅浴室で、交際相手の女性の長男(3)と入浴した際、湯が張られた浴槽内で男児を放置したまま立ち去り、溺死させた疑い。
同署によると、男は、入浴していた男児が玩具を欲しがり、取りに浴室から約20分間離れ、見つからずに戻ったところ、男児がうつぶせで溺れていたと話している。(中略)男は「間違いない」と容疑を認めているという。
保護責任者遺棄致死罪とは
保護責任者遺棄致死罪(刑法219条)とは、保護責任者遺棄罪を犯した結果、意図せず被害者を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
保護責任者遺棄罪は、218条に規定されています。
刑法218条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
保護責任者遺棄罪は、客体と主体が限定されています。
まず、客体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者」です。
幼年者が何歳までを指すのか明確ではないですが、旧刑法336条1項は8歳未満と規定しており、裁判例を見ると2歳から14歳までの実子4人を家に置き去りにした事案で遺棄罪の成立を認めたものがあります(東京地裁昭和63年10月26日)。
本件報道では、死亡した被害者は3歳とのことですから、幼年者にあたると言えるでしょう。
次に主体は「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者」です。
「保護する責任」はどのような場合に発生するのでしょうか?
通説や判例では、法律、契約、条理などが保護責任が生じる根拠としてが挙げられます。
例えば、幼児の世話をしている親は保護責任者に該当しますし、実の親でなくとも子供の世話を依頼しているベビーシッターなども保護責任者にあたります。
本件では、容疑者が交際相手の3歳の息子を浴槽に放置したとされています。
本件の容疑者は保護責任者に該当するのでしょうか。
先ほども述べたように、通説や判例では、法律、契約、条理などの観点から保護責任の有無を判断します。
法律は民法などの法律で規定されているものを指します。
例えば民法第730条では、直系親族は互いに扶け合わなければならないと定めていますので、親は子供について保護責任があると解すことができます。
契約については、委任契約などが当たりますので、ベビーシッターなど子供の世話を委任する契約を結んだ場合には、ベビーシッターにも保護責任があると考えられます。
次に条理ですが、これは社会通念などを指します。
ですので、世間一般的に見て保護責任があると認められるような状況であれば保護責任が認められることになります。
例えば、交際相手の連れ子の面倒を頻繁に見ていた場合、実子や契約に基づいた関係でなくとも、他所から見ると保護責任があるように映るでしょうから、連れ子の場合でも保護責任があると考えられます。
本件報道では、容疑者は3歳の交際相手の息子との入浴途中に当該被害男児を放置して、自分だけ外に出たとされているようです。
報道から察するに、容疑者は被害男児をお風呂にいれていたようですので、被害男児の世話をしていたと解されます。
条理の観点からみて、被害男児の世話をしていたと考えられる容疑者は保護責任者に該当する可能性があります。
「遺棄」とは
保護責任者遺棄罪の行為は「遺棄」と「不保護」です。
両者の違いは、主体と客体との間に場所的離隔が生じるものかどうかで区別されます。
場所的離隔を要する遺棄は、さらに移置と置き去りに分類されます。
移置とは、要扶助者を危険な場所に移転させることをいい、置き去りは行為者が離れていき要扶助者を危険な場所に放置することを言います。
不保護とは、間近にいて世話をしないことです。
本件報道によりますと、容疑者は入浴中に、3歳の被害男児を湯が張られた浴槽内に放置して一人だけ浴室の外に出て行ったようです。
浴槽にどれくらいのお湯が張られていたのかはわかりませんが、3歳の子供では少量のお湯でも溺れる可能性は十分にあります。
1分目を離しただけでもその間に浴槽で溺れてしまうおそれもあり、大人の目がない場所で子供を浴槽に放置する行為は子供の命を脅かす可能性がある危険な行為だといえます。
ですので、本件報道の、3歳の被害男児を浴槽に20分放置したとされている行為は「置き去り」、つまり「遺棄」に該当する可能性があります。
以上より、本件では保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
そして、本件では遺棄の結果、被害男児は死亡しているとのことなので、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
なるだけ早く弁護士にご相談を
保護責任者遺棄致死罪の罰則は、3年以上20年以下の有期懲役であり(刑法219条、218条、205条、12条1項)、非常に重たいです。
また、保護責任者遺棄致死罪が問題となる事件では、殺人の故意があると評価され保護責任者遺棄致死罪ではなく殺人罪が成立してしまう可能性があります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役です(刑法199条)。
殺人の故意がなかったのであれば、取調べ段階で警察官や検察官に対して、その旨をはっきり主張する必要があります。
もし、取調べで殺人の故意があったと受け取られかねない言動をしてしまった場合、それが証拠として用いられて殺人罪が成立してしまうかもしれません。
取調べでどのように対処するかによって、量刑だけでなく成立する犯罪まで変わってしまう可能性がありますから、取調べ前に何をどのように話すか精査する必要があります。
もっとも法律の知識がない人にとって、何をどう話すか精査することは非常に困難です。
そこで、法律のプロである弁護士になるべく早く相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
経験豊富な弁護士になるべく早い段階で会うことで、今後の見通しや取調べに対して的確なアドバイスを受けることができます。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120―631―881にて受け付けております。